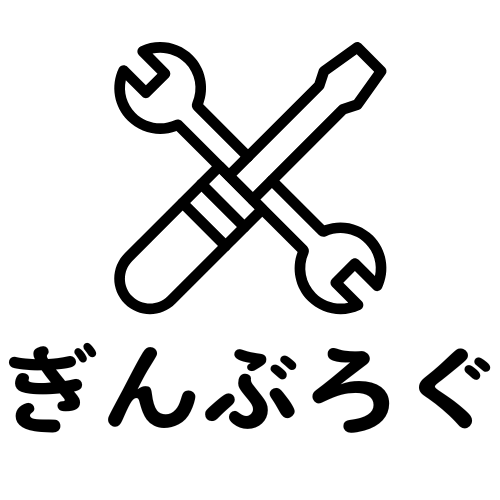夏休みや週末、子どもに植物の水やりを任せたものの
「忘れてた…」で枯れてしまった経験はありませんか?
私も何度も同じ失敗をしました。
そこで今回は、子どもが自分から水やりしたくなる仕組みを
DIYで作ってみました。
お水をあげるとおしゃべりしてくれたり、にっこり微笑んでくれたり
植物が自分の気持ちを表情と声で教えてくれる装置を作ったら
子ども達も、楽しく水やりをしてくれるんじゃなかろうか!
って事で、作ってみましたそんな装置✨
今回は我が家の上の子も(6歳女の子)手伝ってくれたので、親子で楽しめる工作になったかなって思います。
ちなみに、子供たちは最近鉢植えがおしゃべりしてくれるのが楽しくて
毎日欠かさず水やりをしてくれています!
1.なぜおしゃべり植物を作るのか?

子どもは視覚や聴覚からの情報に反応しやすく、「教えてもらう」より「植物が話しかけてくれる」ほうが楽しく学べます。
今回の装置では、土壌水分センサーで植物の水分状態を検知し、不足しているときに声や表情で知らせます。
これにより、
- 水やりのタイミングを感覚で覚えられる
- 生き物を大切にする気持ちが芽生える
- 電子工作やプログラミングの入門になる
といった効果が期待できます。
「お水あげた?」と毎回声をかけるのも疲れるし、かといって親がやってしまっては意味がない。
そんな時、「植物自身が子どもに話しかけてくれたらいいのに」と思いました。
子どもの心を掴む3つのポイント
この装置には、うちの子が夢中になる要素を盛り込みました
- 分かりやすい表情:😊😢😰の3パターンで植物の気持ちを表現
- 声でのコミュニケーション:「ありがとう!」「お水多すぎるよ〜」
- 即座の反応:水やり直後に「ありがとう」と言ってくれる
特に工夫したのは状態変化の検出部分。前回の状態を記憶しておくことで、乾燥状態から適正になった時だけ「ありがとう」と言ってくれるようになっています。これにより、水やりへのご褒美効果が生まれ、子どもたちのモチベーションアップにつながっているはず✨
また、うちの子たちは、プリキュアが大好き!
なので、プリキュア風の画像を画像生成AI先生に生成して頂きました。
こちらをディスプレイに映し出すことにしました!
それにしてもすごい時代ですね、めっちゃプリキュア👇


前回、画像をOLEDディスプレイに入れるやり方をご紹介しました こちら👇
【無料でできる!】OLEDディスプレイ128×64に好きな絵を表示する方法【PhotoFiltre7×Image2cpp活用術】
ちなみに、この子
全部で20種類のセリフをしゃべります。
その中には中二病のようなセリフや
サムライ風のセリフを遊びで1個ずつ入れました。
子ども達にはウケてましたが
妻からは、来客が有った時にしゃべり始めたら恥ずかしいと言われました…。
2.必要な部品と準備
「でも、こういうの作るのって難しそう…」と思われるかもしれませんが、意外とシンプルです!

必要な部品と材料(総額4,000円程度)
- Arduino Uno(互換機):約1,500円
- 土壌湿度センサー:約500円
- OLEDディスプレイ(表情表示用):約800円
- SDカード(音楽を入れる物)約500円
- DFPlayer Mini(音声再生用)&小型スピーカー:約800円
- ブレッドボード&ジャンパー線
あると便利
- 100均のケース(外装用)
- モバイルバッテリー(コードレス化したい場合)
電子工作の外箱はダイソーの樹脂プラBOXを使いました。👇


今回使った植物ポットは、ダイソーから購入したバジル栽培キット👇


3.回路と配線のポイント
回路はとってもシンプル!
土壌水分センサーからの信号をArduinoが読みとって、
値を下回った場合に音声と表情を切り替える仕組み!
OLEDはI2C接続、DFPlayer Miniはシリアル接続で動作します。
実際にArduino互換機とその他電子モジュールを繋いだ状況がこちら👇

4.プログラム(スケッチ)について
Arduino IDEを使って以下のような流れを実装します!
- 土壌水分の値を取得
- 乾燥状態なら音声を再生&悲しげな顔を表示
- 水分が十分なら笑顔を表示&静かに待機
実際のスケッチの核となる部分はこんな感じ
// 湿度センサーの値を読み取り
int moisture = analogRead(sensorPin);
if (moisture > 550) {
// 乾燥時:悲しい顔のみ表示
showImage(sadFace);
lastStatus = 0;
} else if (moisture < 350) {
// 水多時:困った顔+音声
showImage(worriedFace);
if (lastStatus != 2) {
int wetVoice = random(11, 20); // ランダムに音声選択
myDFPlayer.play(wetVoice);
}
lastStatus = 2;
} else {
// 適正時:嬉しい顔を表示
showImage(happyFace);
// 乾燥から適正になった時のみ、ありがとう音声
if (lastStatus == 0) {
int thankVoice = random(1, 10);
myDFPlayer.play(thankVoice);
}
lastStatus = 1;
}
プログラミング初心者のパパママでも、各部分の役割を理解しながら進めれば大丈夫かと!
作業時間
- プログラミング経験あり:半日程度
- 初心者パパママ:週末2日間程度
- 子どもと一緒に:楽しみながら1週間
5.実際に動かしてみた感想

土壌湿度センサーをプスッとポットの土に差して実験開始!
子供たちから、じょうろでお水をあげてみると
悲しい顔 → にっこり へ表情変化成功!
お水ありがとうセリフも再生成功!
更にお水をあげ続けると
にっこり → 困り顔 へ表情変化成功!
お水多すぎるセリフも再生成功!
期待通りの動作をしてくれてよかったです。
数日間使っていると子供たちにも変化が有り
子どもが自分から「お水あげなきゃ!」と行動するようになりました!
私も作業を通じてセンサーの仕組みやプログラミングの基本を自然に学べました!
6.子どもの反応と学び
お水をあげて、音声が再生されるのが楽しかったようで「植物がしゃべった!」と笑顔に
そのうち、土壌湿度センサーを土から引っこ抜いて差す事で値が変わり、
音声がされる事を覚えちゃったので、何度もプスプスとセンサーを土に刺してました。
でもこれで、水やりのタイミングを覚えられるので
乾燥→給水→笑顔の流れを体験で学べたのかなと思います。

子どもと一緒に作る学習効果
うちの子は、電子工作の外箱、スピーカー部分の加工を手伝って貰いました!👇


背面はこんな感じ👇

うちの子達はまだ小さいので、もっと大きい子達ならこんな効果があるかも👇
プログラミング的思考
「もし土が乾いていたら→悲しい顔を表示する」といった条件分岐の考え方が自然に身につきます。
科学的観察力
「なぜセンサーの数値が変わるのか?」「水をあげるとどう変化する?」といった疑問から、科学への興味が広がります。
ものづくりの達成感
「自分が作った装置で植物が元気になった!」という体験は、何物にも代えがたい自信につながります。
📱 忙しいパパママへのアドバイス
時間がない場合
まずは既製品のスマート植物センサーから始めて、お子さんの反応を見てから手作りに挑戦するのもアリですね!
🚀 さらなる発展アイデア
子どもたちからも「こんな機能があったらいいな」というアイデアが!!
- 天気予報連動:雨の日は水やりお休み
- 成長記録:植物の成長をグラフで表示
- 複数植物対応:家中の植物を管理
- スマホ通知:外出先からも植物の様子をチェック
💭 パパママへのメッセージ
電子工作・プログラミング・自然観察の3つが一度に楽しめました。
この装置を作って一番感じたのは、「子どもは適切なきっかけがあれば、自分から学び、成長する」ということです。
何より、親子で一緒に作り上げたものには、市販品では得られない特別な価値があります。
「うちの子にはまだ早いかな?」なんて思わずに、ぜひ挑戦してみてください。子どもたちの予想以上の反応に、きっと驚かれると思いますよ😊
「子どもが変わる」「家族の時間が増える」「学習効果も抜群」
そんな一石三鳥の手作りガジェット、あなたも作ってみませんか?
また、DFplayer mini の使い方を詳しく解説した記事も有りますので
ご興味が有れば覗いてみてください👇
初心者向け|DFPlayer miniの使い方解説!Arduinoなしで音声再生DIY入門